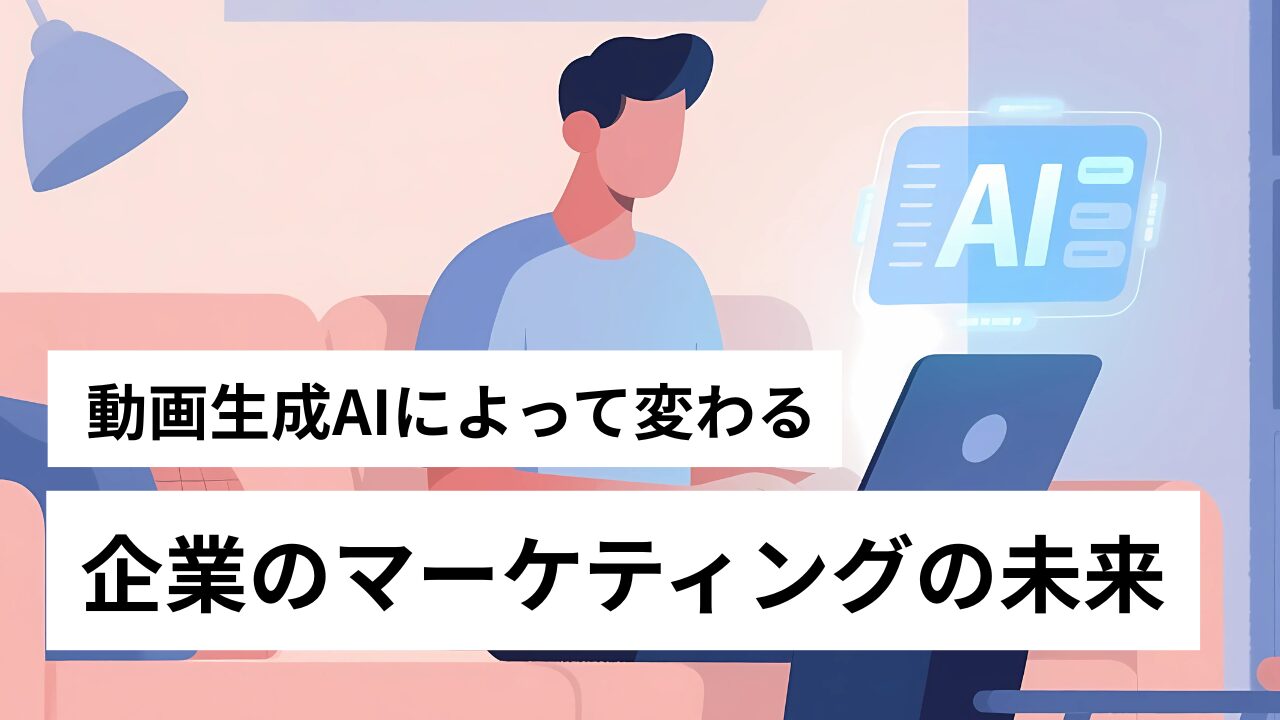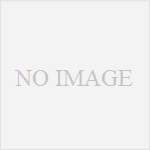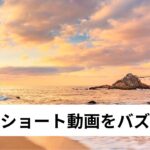今週、OpenAIが公開した「Sora2」。
これまでの動画生成AIは未だに『AIっぽさ』がかなり残る仕様になっていましたが、今回リリースされた「Sora2」はそれまでのものと一線を課すリアルさで生成することが可能になりました。
動画マーケティングを主事業としている弊社にとっても、この「Sora2」は正直言って、動画業界にゲームチェンジを起こす兆しが一気に見えてきたほどの衝撃を感じました。
そこで今日は、企業のマーケティング活動を大きく変えつつある「動画生成AI」について、最新の動向をまとめてみました。
「AI」という言葉は日常的に聞くようになりましたが、「動画生成AI」と聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。簡単に言えば、文字で指示を出すだけで、AIが自動的に動画を作ってくれる技術のことです。
まるでSF映画のような話ですが、もう実用段階に入っているんです。
動画生成AIって、具体的に何ができるの?
ここ最近注目されているのが、「Sora2」という動画生成AIです。このSora2、何がすごいかというと、ひとつに物理法則を理解している点が挙げられます。
たとえば、「コップから水がこぼれる様子」を生成するとき、水の流れ方、重力の影響、コップとの衝突の様子まで、まるで本物のようにリアルに再現できるんです。
以前のAI技術では、水が不自然に浮いたり、物理的におかしな動きをすることがありましたが、Sora2ではそういった違和感がほとんどありません。
さらに驚くのが「Cameo機能」
これは、あなた自身の顔写真をアップロードすると、AIが学習して、あなたが登場する動画を作ってくれるという機能です。
もちろん、勝手に芸能人の顔を使ったりできないよう、厳格な制限がかけられています。
そして、映像だけでなく声や環境音まで同時に生成してくれます。ナレーションやBGMを別途用意する必要がないんですね。こうした技術により、20秒程度の高品質な映像が、驚くほど短時間で完成するようになりました。
コストがかかりすぎる従来の動画制作
企業が動画を作ろうとすると、従来はどれくらい大変だったのでしょうか。
まず、企画段階で何度も打ち合わせを重ね、脚本を作成します。
その後、撮影場所(スタジオや屋外ロケ地)を確保し、カメラマンや照明スタッフ、出演者(モデルや俳優)を手配します。撮影当日は機材を運び込み、何時間もかけて撮影。
そこから編集作業に入り、カット割り、色調整、テロップ入れ、BGM選定…と、やることが山積みです。
PR Timesの発表によると、こうした一連の作業に約20時間を要し、業界によっては1本あたり数十万円から数百万円規模の費用がかかっていたそうです。
中小企業にとっては、なかなか手を出しづらい金額ですよね。
AIを使うと、コストと時間がどれくらい変わる?
動画生成AIを導入すると、この状況が劇的に変わります。
PR Timesが提供する生成AIサービス「PROMO AI」では、撮影や照明、スタジオやモデルの手配といった従来必要だった工程を省き、3〜5営業日で納品できるとしています。つまり、約1週間以内に動画が完成するということです。
米国の事例では、もっと具体的な数字が出ています。AdVidsという企業の試算によると、従来の動画制作が平均2万6千ドル(約380万円)・4週間かかるのに対し、AIを用いた制作では約4千ドル(約60万円)・0.5週間で完成するそうです。
計算してみると、費用が約6分の1、制作期間が8分の1に短縮される計算になります。これは本当に革命的な変化だと思います。
さらに印象的なのが、IT管理プラットフォームのAteraという企業の事例です。
広告キャンペーンの映像をSoraやMidjourney(画像生成AI)を活用して制作したところ、通常3〜4か月かかる映像制作が約4週間で完成し、従来なら100万ドル(約1億5千万円)規模と見積もられた制作費も大幅に削減できたと報告しています。
A/Bテストも簡単にできる時代に
「A/Bテスト」というのは、2つの異なるパターンの広告を用意して、どちらの反応が良いかを比較検証する手法です。
従来は、複数パターンの動画を作ろうとすると、その分だけ時間とコストが倍増していました。しかしAIを使えば、同じ内容で色違いのバージョン、テロップの位置を変えたバージョン、BGMを変えたバージョンなど、多数のバリエーションを瞬時に生成できます。
これにより、マーケターは試行錯誤の速度を上げ、トレンドへの反応時間を短縮できるようになりました。
SNS広告では、わずか数日でトレンドが変わることもありますから、この迅速性は大きなアドバンテージになります。
マーケティングチームの働き方が変わる
動画生成AIの導入は、単なるコスト削減以上の意味を持っています。チーム全体のワークフローが変わるんです。
Ateraの事例を見ると興味深いです。
マーケティングチームは、コンセプトや脚本などクリエイティブな企画に集中し、AIが視覚素材の生成を担当したそうです。
つまり、「どんなメッセージを伝えたいか」「どんなストーリーで視聴者の心を掴むか」といった、人間にしかできない戦略的思考に時間を使えるようになり、技術的な撮影作業はAIに任せる、という分業体制が確立されたということです。
同じように編集工程でも変化が起きています。
字幕生成(話している内容を自動的に文字起こししてテロップにする)、シーン検出(動画の中で場面が切り替わるポイントを自動認識)、色調補正(映像全体の色味を整える)といった、これまで手作業で行っていた単純作業がAIにより自動化されています。
ただし、ここで重要なのは、すべてがAIに置き換わるわけではないという点です。感情に訴える演出やストーリー構成など、創造的な作業は依然として人間が担います。
AIはあくまでアシスタント的役割に留まり、人間の共感力と温かみを組み合わせたハイブリッド型のアプローチが重要になってくるでしょう。
パーソナライズ動画の可能性に注目
個人的に最も注目しているのが、パーソナライズ動画の可能性です。
「パーソナライズ」というのは、一人ひとりに合わせてカスタマイズするという意味です。
たとえば、Amazonで買い物をすると、「あなたへのおすすめ」が表示されますよね。あれと同じように、動画も個人に合わせて内容を変えることができるんです。
日本のパーソナライズ動画サービス「PRISM」では、顧客データ(名前、購入履歴、興味関心など)を読み込み、シナリオやメッセージ、映像を自動的に最適化して、各顧客向けの動画を生成します。
驚くのはその規模です。数千〜数万本のパーソナライズ動画を自動生成し、その結果を分析して改善することも可能だそうです。
従来、こんなことは人手では絶対に不可能でしたが、AIなら実現できます。
海外の調査では、ハイパーパーソナライズされたマーケティングは顧客獲得コストを最大50%削減し、ロイヤルティやエンゲージメント(顧客との結びつきの強さ)を高めるとのこと。
特に若い世代の反応が顕著です。
Gen Z(1990年代後半から2010年代前半生まれの世代)の93%、高所得層の88%がパーソナライズ動画を望んでおり、93%がインタラクティブ動画(視聴者が選択肢をクリックして展開が変わる動画)への関心を示しているというデータもあります。
TikTok ShopやInstagram Shoppingなどでは、動画を見ながらそのまま商品を購入できる仕組みが整っており、コンバージョン率(実際に購入に至る割合)は従来比1.5〜2倍に達しているそうです。
ブランド戦略にも大きな影響
動画生成AIは、企業のブランド戦略にも大きな影響を与えています。
高品質かつ斬新な映像でメッセージを効果的に伝えられるようになり、しかも短期間で制作できるため、市場の変化やトレンドに素早く対応できます。
競合他社より早くAI活用を進めた企業は、新しい広告手法を次々と試すことで競争優位を確保できるわけです。
ここで、日本企業の事例をいくつかご紹介します。
伊藤園は2024年に生成AIモデルをCMに登場させました。実在の人間と見分けがつかないほど高品質な映像を実現し、SNSで大きな話題となったそうです。
電通デジタルが開発したバナー生成AI「ADVANCED CREATIVE MAKER」は、なんと5秒で1案を生成し、1,000点以上を迅速に制作できるとのこと。これまで何日もかかっていたバナー制作が、ほんの数時間で完了するようになったわけです。
セブン‑イレブンでは、ChatGPTで店舗販売データやSNSの反応を分析し、商品開発期間を90%短縮したという事例もあります。
また、メール文面を生成AIでパーソナライズしたところ、開封率とクリック率が向上し、コンバージョン率が82%増加したという報告もあります。
動画生成AIの活用で注意すべき点
そういった便利な動画生成分野のAIですが、いくつか懸念すべき点もあります。
その際たるが、プライバシーや著作権への配慮です。
ヨーロッパのGDPRやカリフォルニアのCCPAといった個人情報保護規制があり、顧客データを使ってパーソナライズ動画を作る際には、適切な同意取得と管理が必要です。
AIが学習に使うデータに著作権で保護された素材が含まれていないか、生成された動画が既存の作品に似すぎていないか、といった点もチェックが必要です。
アルゴリズムの透明性や倫理への取り組みを怠ると、ブランドの信頼が損なわれるリスクもあります。
顔認証技術の倫理的問題Sora2の「Cameo機能」のように、個人の顔を動画に登場させる技術も、プライバシーの観点から慎重な扱いが必要です。
この技術自体は、本人が自分の顔を使って楽しむ分には問題ありません。
しかし、他人の顔を無断で使用するリスクが常に存在します。芸能人やインフルエンサーの顔を勝手に使ってフェイク動画を作り、あたかも本人が特定の商品を宣伝しているかのように見せる。
これは明らかな権利侵害であり、場合によっては犯罪行為になります。OpenAIは、こうした悪用を防ぐために制限を設けていますが、技術が進化すれば抜け道を探す人も出てきます。企業としては、こうした技術を使う際に、倫理的な配慮を怠ってはいけません。
動画生成AIのこれからの展望
今後、動画生成AIはさらに進化していくでしょう。
リアルタイム生成(その場で即座に動画を作る)や即時パーソナライズが可能になり、動画を見ながら商品を選んで購入できる仕組みが一般化していくと予想されます。
法規制や倫理基準が整備されるにつれ、ユーザーと企業の信頼関係を保ちながら革新的なマーケティングが展開されるでしょう。
日本企業にとっても、この技術の進化を積極的に取り入れることが重要です。データ分析の力とクリエイティビティを融合させた新しいマーケティング戦略を構築することが、これからの競争を勝ち抜く鍵になると思います。
動画生成AIは万能ではありませんが、適切に活用すれば、より豊かなブランド体験を創出する強力なツールになります。
AIと人間が協働することで、私たちが想像もしなかった新しいマーケティングの形が生まれるかもしれません。
あなたの会社では、動画生成AIの活用について検討されていますか?
まだ導入していない場合でも、まずは無料のツールで試してみることから始めてみるのもいいかもしれませんね。